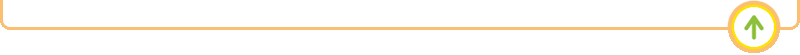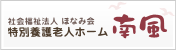理事長の思い
- Jan
- 27
12 アルツハイマー病の人びとの祈り
3つの詩をご紹介します。
アルツハイマー病の人たちが書いた詩です。
「南風」の職員向けに試訳しました。
アルツハイマー病者の祈り
(Alzheimer's Prayer)
作者不明
神様
訪れてくれる人びとに、わたしの混乱を受け入れる力をお与えください。
わたしの理不尽な行動をゆるす力をお与えください。
そして、かすみのかかった記憶の中をわたしと共にあゆむ力をお与えください。
たとえ訪れてくれる人びとが誰かわからなくても、
その人がわたしの手をとり、しばし一緒に時を過ごせるようお導きください。
あなたがたの忍耐と思いやりは、
いつか、わたしがそれを最も必要とする日々のなぐさめとなっていくでしょう。
訪れてくれる人びとに教えてあげてください ―
彼らが誰かわからなくても、わたしは努力していることを。
彼らがわたしのために悲しまないようお導きください。
わたしの嘆きはそのいっときだけであり、すぐに消えていくでしょう。
最後に、神様、
訪れてくれることがいかに大切であるかを彼らに教えてあげてください。
このきびしい神秘の世界にあっても
わたしには彼らの愛情が感じられるのです。
アルツハイマー病者の祈り
(Alzheimer's Patient's Prayer)
キャロライン・ハイナリ
わたしのために祈ってほしい
かつて、わたしもあなたのようだった。
やさしく、思いやりをもって接してほしい
いつもわたしがそうしていたように。
思い出してほしい
かつてわたしも人の親であり、妻であり、
そして人生があって、夢があった。
わたしに話しかけてほしい
たとえ内容がわからなくても、声は聞こえる。
わたしに話しかけてほしい
もしかしたら思い出すかもしれない。
わたしのことを思いやってほしい
わたしの日々は苦労に満ちていた。
わたしの気持ちをくみ取ってほしい
いまでも感情はのこり、痛みを感じている。
心をこめて接してほしい
わたしもあなたにそうしてきた。
アルツハイマー病になる前のわたしがどうであったか思い出してほしい
わたしは活気にあふれ、人生と笑いがあり、そしてあなたを愛していた。
いまのわたしはどうなってしまったか
病のために感情や考える力、答える力がゆがんでしまった。
しかし言葉にはならないが、いまでもあなたを愛している。
わたしの将来を思ってほしい
なぜなら、わたしはいつも思っていたのだから。
思い出してほしい
わたしにもあなたと同じように希望があったことを。
さまざまな思いが頭の中にとじ込められ、外に伝えることができない
それがどんなにつらいかを考えてほしい。
わたしのことをわかってほしい
つらく当たらないでほしい ― 責められるべきはアルツハイマー病だ。
いまでもわたしは思いやりと触れあいを求めている
そして、なによりも、あなたに愛されることを求めている。
祈りのなかに、どうかわたしを加えてほしい
なぜなら、わたしは生から死への旅上にいるのだから。
あなたが示してくれる愛情は神様からのお恵みだ
だからわたしたちは永久に生きられる。
今日、あなたがどう生きるか、何を行うかは
わたしたちアルツハイマー病者の心にいつまでも残っていく。
わたしの靴をはくまでは
(Till You Walk in My Shoes)
キャロライン・ハイナリ
あなたはわたしの痛みを知らない
痛みがあることさえもわからない
あなたにはわたしのまなざしに浮かぶ痛みが見えない
だって、わたしの境遇にいないのだから
いつもそばにいて手を握ってくれるわけではなく
わかってくれることもない
わたしの靴をはくまでは
心の痛みを訴えても
あなたは聞こうとしない
聞くためのわずかな時間もとってくれない
だから、あなたにはわからない
わたしの靴をはくまでは
むかしの話をしても、あなたはとり合ってくれない
思い出が色あせていくのに、だれも気にかけてくれない
忙しすぎて、わたしの泣き言など聞いていられないのだろう
ただ無視しつづけている
しかし、いつの日か、きっとあなたにもわかるだろう
そして、そばにいて手を握らなかったことを悔やむでしょう
わたしの目をのぞくと見える空虚さ
「あなたはだれ?」と尋ねられたときの無力感
あなたにはわたしの心の痛みがわからない
わたしの靴をはくまでは
現実に引き戻そうとするとき
あなたは不思議に思うでしょう
はたして時がどこまで遡ってしまったのか
だから残っている時間を大切にしよう
すぐに消えていくのだから
アルツハイマー病には慈悲のかけらもない
記憶をごっそり奪いとっていく
それは、だれにでも、いつでも起こり得る
いま、はじめて知ったかもしれないが
あなただって、いつか、わたしの靴をはいて歩くのです
- Jan
- 08
11 わかってもらえなければ人は頑張れない
【若いころ、社会福祉の分野で職を得た私は、大段智亮先生の本を読みあさっていま
した。いま振り返ってみると、それは仕事上必要だった対人関係の知識を学ぶためと
いうよりも、自分の生き方を確かめるためだったような気がします。
じつは私の職場には大段先生のことを個人的によく知っている大先輩がいて、いつも
先生のことを話してくれました。それがきっかけとなって先生の著書に魅かれていった
のだと思います。
この文章は、尊敬する大段智亮先生が援助的人間関係について語っている著書を参
考・引用して、私の個人的感想を述べたものです。といっても家庭の事情ですべての
著書を手放してしまったので、書名も思い出せず、どこまでが正確な引用なのかも分
かりません。私が社会福祉の仕事を選んでから三十余年が経過しました。困ったとき
はいつも(お会いしたこともない)先生に支えられてきたことを感謝いたします。】
長期ケア施設で暮らしているお年寄りは「もう死にたい」とよく口にします。あるいは、もっと遠回しに、「はやくお迎えが来てほしい」「はやくおじいさんの傍へ行きたい」とつぶやきます。なかには、ニコニコしながら、まるで挨拶代わりのようにそう言う人もいます。そのためでしょうか、施設のなかにはホールの壁に次のような言葉を掲示しているところもあります。「八十でお迎えが来たら、まだ早いと言いなさい。九十でお迎えが来たら、そう急がなくてもいいと言いなさい ...」
お年寄りがそう言うときは、やさしく声をかけ、いっしょにお茶を飲むと気分転換になることがあります。問題なのは、深刻に、追い詰められたような表情で「もう死にたい」と訴える場合です。たとえば、夜みんなが寝静まったときに、あなたが寝たきりの入居者からそう訴えられたらどうでしょう。慰めや励ましの言葉を見つけることができますか?
施設で暮らしている寝たきりのお年寄りが、「こんなふうなら、もう死んだほうがましだ」と深刻な表情でつぶやいたとします。それに対する職員の言葉として、以下の4つを考えてみましょう(以下の文章の一部は大段智亮先生の著書を参考・引用しています)。
職員1 「じゃあ勝手にしたら」
職員2 「なに言っているの、縁起でもない。生きていれば必ずよいことがあるわ」
職員3 「あなただけよ、そんなことを言うのは。まわりの人を見てごらん。みんな我慢して頑張ってい
るのよ」
職員4 「つらいんだね。だから死にたくなったんだね」
以前、私がいろいろな施設や病院の職員にアンケートでたずねたところでは、ふだん多くの人が「職員2」「職員3」のように答えているようです。もちろん「職員4」が正解らしい(?)とは思っているのですが(看護・介護の教科書には「傾聴」と「受容」と「共感」が大切だと書いてあるから)、実際の場面でそのように対応する人はごくまれです。
当然のことですが、そう思うか思わないかは別にして、施設や病院のスタッフのなかで「職員1」のように答える人は皆無です。しかし家族のなかには、じかに面とむかって「そんなこと言うのなら勝手に死んだら」と告げる人がいます。その場に居合わせると、どきっとする言葉です。しかし、身体の弱った老親から毎日「死にたい」と訴えられ、介護を代わってくれる人がいない厳しい状況下で、家族がそう言いたくなるのも理解できないことではありません。それは孤立無援の戦いを強いられている家族のせっぱ詰まった叫び声です。それに比べて、施設や病院の職員は勤務が終われば自由になれるのです。ですから、もしこんなことを口にする職員がいたとしたら大問題です。
それでは、つぎに慰めや励ましの具体例として「職員2」について考えてみましょう。この発言には2つの意味が込められています。一つは「なに言ってるの、縁起でもない」という言葉です。それは「縁起でもないことは言ってはいけない」というメッセージとなって相手に伝わっていきます。ですから、そう言われたお年寄りは、それ以上なにも口にすることができません。せっかく喉まで出かかったつらい気持ちを飲み込まなければなりません。それがどれほどつらいことか、想像できますか。
もう一つは、「生きていれば必ずよいことがあるはずだ」という言葉です。これは他人に対して人生訓を垂れるのと同じことで、それ自体が問題を含んでいるのですが、はたして職員は心からそう思って言っているのでしょうか? おそらく、そうではありません。私たちはお年寄りが「死にたい」と言いはじめると、最後まで聞かないうちに相手の言葉を遮って、「大丈夫、大丈夫」「頑張ろうよ」と無条件に反応してしまう傾向があります。あたかも、お年寄りの言葉でとっさに不安になってしまった自分自身を励ましているかのようです。これでは、どっちがつらいのか分からなくなってしまいます。
「職員3」の発言はどうでしょう。「みんな頑張っているのだから、あなたも頑張れるはずだ」と言われて、それを慰めや励ましと感じる人がいるでしょうか? 母親が遊んでばかりいる小学生の弟にむかって、「あなたもお兄ちゃんのようにしっかり勉強すれば、よい成績がとれるはずよ。頑張りなさい」と言ったとします。そのとき、弟はどう反応するでしょうか? 「そんなこと言ったって、ぼくとお兄ちゃんは違うのだから」と反発するに決まっています。私たちは困っている人を励まそうとして善意でこう発言するのですが、他人と比較されて頑張る人はいません。
「職員4」のように、「つらいんだね。だから死にたくなったんだね」と答えると、どうなるでしょう? こんなふうに言ってくれるのは(大勢の職員のなかで)あなただけです。なぜなら、他の人は、「がんばれ!」「大丈夫!」としか言ってくれないのですからです。
相手が「つらい」と言ったら「つらいんだね」と答え、「死にたくなった」と言ったら「死にたくなったんだね」と答える方法と、相手が「つらい」と言っているのに「つらいことなんかあるものか」「大丈夫だ」「がんばれ」と答えたり、「死にたい」と訴えているのに「そんなことを考えてはだめよ」「生きていることに意味があるのだから」と答える方法では、その間に天と地の差があります。お年寄りはその違いを敏感に感じとり、だれが心底親身になってくれる職員であるかを知っていくのです。
「大丈夫、大丈夫」「がんばれ、がんばれ」と叱咤激励されず、「生きていることに意味がある」と説教もされず、そのつらさを無条件に受け入れてもらえると、その人は自由に感情を表出することができるようになります(バイスティックの『ケースワークの7つの原則』にも、この感情表出の大切さが述べられています)。もしかしたら感情が高ぶって、泣き出してしまうかもしれません。そして、最後には言葉を失い、しばらく沈黙してしまうでしょう。
深刻な場面で沈黙が続くと、私たちはどうしたらいいか分からなくなっていきます。その緊張感と苦しさに居たたまれなくなってしまいます。そして沈黙の重さに耐えきれずに、私たちのほうから「大丈夫、大丈夫」「がんばれ、がんばれ」と余計なことを口走ってしまうのです。
相手が沈黙したとき、私たちに必要なのは、黙ってその場にいてあげることです。これには勇気がいります。神学者のポール・ティーリッヒは、その場に居続けることを「存在する勇気(the courage to be)」と呼んでいます。もし可能なら、泣き黙ってしまったお年寄りの手をとり、肩を抱いてあげるとよいでしょう。
【余談ですが、ちなみにハムレットもこの「存在する勇気」と似た科白を口にしています。「To be, or not to be, that is the question」。ふだん「生きるべきか、死ぬべきか、それが問題だ」と訳されるこの言葉は、「このままここに居続けるべきか、それとも居続けざるべきか、それが問題だ」と訳すことも可能です。】
「死にたい」という思いにとらわれて泣き出してしまったお年寄りも、いつかは泣きやみます。そのとき、その人の気持ちはずっと軽く(楽に)なっているはずです。そして、ふと、目の前にいるあなたに気づいて、こう言うでしょう。「あなたって、いい人ね。あなたみたいないい人がここに居るのだったら、わたし、もうちょっと頑張ってみるわ」と。そのとき初めて、私たちは、「そうだね、いっしょにがんばろうね」と言ってあげられるのです。このときの「がんばろうね」という励ましの言葉は、かならず相手の心に届きます。なぜなら、その人が自ら「がんばりたい」と言っているのですから。
つらい立場にいる人は、ひとりでは生きられません。真っ暗な、ひとりぼっちの世界に置かれているからです。しかし、本当に理解してくれる人が一人でもいたら、その人は生きられます。なぜなら、もうひとりぼっちではないからです。そこには良い人間関係が存在しています。この温かい人間関係をとおして、心のなかに、生きるエネルギーが徐々に湧いてくるのです。
こうしたことは、その人の悩みをそのまま受け入れてあげることから生じます。悩みに共感し、それを受容することが大切です。私は、ふだんの仕事のなかで、お年寄りから「あなたにわかってもらってうれしい」と言ってもらえるような、そういう人になりたいと思っています。私たちが取りくんでいる「ケア Care」」には、他者を気づかい、思いやるという意味が込められているのです。
- Sep
- 24
10 記憶していなければ答えられないことを質問してはいけない
ふだん面会に訪れるご家族の多くが、認知症の老親(入居者)にむかって同じような言葉をかけています。どのような言葉かというと、顔を合わせるなり、「わたしが誰だかわかる?」と尋ねるのです。そこで、以下のような会話を作ってみました。
例1: 施設で暮らしている認知症の母親と、毎日面会に訪れる娘の会話
娘「お母さん、面会に来ましたよ。わたしが誰だかわかる? 名前を言ってみて?」
母「 ... 」
娘「どうしたのよ。わたしの名前を言ってみて」
母「 ... 」
娘「忘れちゃったの? だめじゃない。自分の娘でしょう! わたしの名前は?」
母「 ... どうしてそんなことを聞くの? ... 」
娘「しっかりしてよ。忘れちゃダメでしょう! 思い出して言ってみて」
母「 ... いいじゃない、そんなこと ... 」
娘「 いいわけないでしょう! 自分の娘なのよ!」
母「 ... もういいよ。帰ってよ! ... 」
せっかくの面会なのに、母親も娘もイライラし、ケンカになってしまいます。なぜこうなるのでしょう?
例2: 施設で暮らしている認知症の母親と、毎日面会に訪れる娘の会話
娘「お母さん、面会に来ましたよ」
母「あー、お前じゃないか。久しぶりだねえ。長いこと来てくれないので、何かあったんじゃない
かと配していたんだよ」
娘「なに言ってるのよ。毎日ちゃんと面会に来ているじゃない!(ベッド横のカレンダーを指さし
て)カレンダーを見てごらん。昨日も、その前の日も、ちゃんと赤いマルがついているでしょ
う。わすれちゃったの?」
母「だって ... お前のことが心配だったもんで」
娘「他人(ひと)のことより、自分のことを心配したら」
母「 ... 」
娘「お母さん、しっかりしてよ。少しボケが進んだんじゃない?」
母「 ... もういいよ。帰ってよ! ... 」
こうして、楽しいはずの面会が台無しになってしまいます。おそらく娘さんは「もう二度と来るもんか」と穏やかならざる心境になっているでしょう。
小澤勲著『痴呆を生きるということ』(岩波新書)によると、認知症の人には中核症状としてのもの忘れがあり、それが私たちにとって不都合な、理解しにくい行動(周辺症状)を引き起こしていくそうです。ただし、もの忘れのある人のすべてがそうなるわけではなく、そうなるには相手をイライラさせてしまう私たちの接し方(ケアのあり方)が介在していると言うのです。
「例1」の母親には、もの忘れがあります。娘の名前を思い出すことができません。記憶から向け落ちてしまったのです。それなのに「名前を言いなさい」と強く要求されつづけます。母親としては、「ごめんなさい。あなたの名前、忘れちゃった」と正直に告げることができれば、おそらく気持ちもすっきりするでしょうが、それはできません。なぜなら、どこかで見覚えのある、せっかく来てくれた人に対してそんなことを言うのは失礼だと感じているからです。たとえもの忘れがあっても、認知症の人びとは私たちと同じ感情を保っています。それゆえ、追い詰められた苦しさのあまり、「もういいよ。頼むから、そんなことは聞かないでくれ」と訴えるのです。そうした苦しい気持ちを感じ取れずに(それは私たちの鈍感さを証明している)、もし私たちが質問責めを行うとしたら、最後にはイライラしてきて、「もう帰ってよ」と言わせてしまうことになるのです。
では、面会に来た娘さんは、どのように言葉をかけてあげたらいいのでしょう。「わたしの名前を言ってごらん」と質問するかわりに、もし娘さんが「わたし、娘の○子ですよ」と、まず自分から名のってあげたら、おそらく母親は「あー、○子じゃないか。よく来てくれたねえ。うれしいよ」と答えるにちがいありません。こうして楽しい面会がはじまっていきます。
「例2」はどうでしょう。母親が「お前が長いこと来てくれないので、何かあったんじゃないかと心配していたんだよ」と言ったとき、「お母さん、心配かけてごめんね。毎日ちゃんと来るからね」と答えたとしたら、おそらく母親は「ありがとう。お前だけが頼りだから」と続けるでしょう。こうして親子のきずなを確かめあう、すてきな面会がはじまっていくのです。
老親に認知症がはじまると、子供がその進み具合を心配するのは当然です。それで、いろいろ質問してみたくなるのです。しかしもの忘れがあるのですから、忘れてしまったことは答えられません。
質問するかわりに、こちらから、抜け落ちてしまった記憶をおぎなってあげるほうが良い援助につながります。「記憶していなければ答えられないことを質問してはいけない」 ― これはケアの鉄則なのです。あなただって答えられないことを質問されつづけたら、おそらく惨めな気持ちになっていくでしょう。
最後に、以前このコーナーで紹介した「The 36-Hour Day」(ジョンズ・ホプキンス大学出版)という家族介護者向けの本の一部を抜粋します。これは、もの忘れが進み、体力も衰えたため家で暮らせなくなった老婦人「メアリーの事例」です。
「(施設へ移ってからの)メアリーにとって最もうれしかったのは、家族が面会に来てくれることでした。メアリーは、たまには家族の名前を思い出すこともありましたが、たいていは思い出せませんでした。一週間前に訪問してくれたことも覚えていません。それで、ときどき、家族に見捨てられてしまったと愚痴を言っていました。そんなとき、家族は答えに窮しましたが、それでも彼女の弱った体に腕をまわし、手を握ってあげました。あるいは、黙ってそばに座り、ときには歌をうたってあげました。メアリーにとって有難かったことは、家族が、ついさっきメアリーが口にしたことや、先週面会に訪れたことを、むりやり思い出させようとしなかったことです。また、この人は誰、あの人は誰と、矢継ぎ早に彼女に質問を浴びせることもありませんでした。メアリーのなかでは、家族に抱きしめてもらったり、やさしく接してもらうときが最高の時間だったのです。」 (筆者訳)
- Sep
- 18
9 認知症の人びとについて教えてくれた4冊の本
ずっと昔、私が高齢者の医療福祉に関心をもちはじめたころ、認知症の人びとに対するケアという言葉を耳にすることはありませんでした。病院や施設の職員は認知症の人びとの「予期せぬ」行動に振りまわされ、戸惑うばかりでした。現場では「問題行動の抑制」が主な関心事で、そのため上手に身体拘束できる職員が羽振りをきかせ、逆に「手を縛ってごめんね」などと素直にあやまっている職員は隅に追いやられている状態でした。
はじめて訪れた「老人のための病院」では、床にゴザを敷いただけの、ものが一つもない大部屋の中に、カギ付きの「つなぎ服」を着せられたお年寄りが詰め込まれていました。それは「生活の匂い」とは無縁の、ただ収容管理だけを目的とした現代の「救貧院」でした。こうした社会から隔絶されたところに、家族でもない一般市民が足を踏み入れることはほとんどありませんでした。多くの人にとって、それは窺い知ることのできない(あるいは知りたくない)別世界だったのです。やむをえず面会に訪れたとしても、通路を歩くだけで体内に沁み入ってくる老いの無慈悲さに息を凝らしたことでしょう。
その後、病院や施設の数が増え、新たに「中間施設」が作られ、そして福祉先進国の情報が入るにつれて、認知症の人びとに対するケアのあり方も徐々に変化していきました。とはいっても、相変わらず「職員の都合」によるケアが業務の中心を占めていて、そこに少しずつ、専門性をよそおった様々なタイプのセラピーが導入されていきました。こうして認知症ケアは科学性を帯びていったのですが、職員が上から施すケアに変わりはありませんでした。
認知症の人びとと接するようになった当初、私はその異質とも思える世界に困惑していました。しかし、こちらの価値観を横に置いて接することができるようになると、次第にその不思議な世界に魅せられていきました。そして今、私は、彼ら(彼女たち)と共に時間を過ごせることを感謝しています。
認知症の人びとは私にとって「癒し人」です。いつも正直に私たちのことを見ています。ですから嘘がつけず、謙虚にならざるを得ません。自分のいい加減さを思い知らされると同時に、ほっとする安らぎを与えてくれます。そのような気持ちにさせられるのも、おそらく認知症の人びとが、もはや社会的地位や身分によって他者と付き合っているのではないからだと思います。彼らはひとりの人として、他者のなかに人を求めているのです。
これまで認知症に関する本をいろいろ読んできましたが、そのほとんどが「こんな場合にはこう接しましょう」というケアのノウハウを述べているだけでした。そして、そのマニュアルどおりに実行するだけで満足していたのです。しかし、いつも心の底には、本当にこれでいいのだろうか、相手はどう思ってくれるだろうかという不安な気持ちが存在していました。
そんなとき、認知症の人びとの気持ちを垣間見させ、もっとその人の立場に立った援助を教えてくれる本に出会いました。『The 36 Hour Day』というアメリカの本です(ジョンズ・ホプキンス大学出版)。それが従来の本と異なっていることに気づいた私は、なんとしても仲間に読んでほしくなり、辞書を頼りに第1章から訳しはじめ、みんなに配布し、(途中で挫折してしまいましたが)読書会を行いました。なんとも無謀な、なつかしい思い出です。そのときの仲間は、今でもみんな「南風」を応援してくれています。この本は今日にいたるまで版を重ね、非常に長期にわたって読みつがれているそうです。
私が特別養護老人ホーム「南風」をスタートさせたころ、オーストラリアの認知症の女性、クリスティーン・ボーデンの著書が日本でも出版されました。『私は誰になっていくの? ― アルツハイマー病者からみた世界』(クリエイツかもがわ)という題名のこの本は、はじめて当事者が書いた画期的な本で、強い衝撃を受けました。認知症と診断された女性が、認知症と共に生きるとはどういうことかを教えているのです。日ごろ私たちが行っている些細なことで ― 私たちはそれを正しい援助だと思っています ― 彼女たちが混乱し、傷ついていく様子が描かれています。認知症の人びとの気持ちに寄り添うことがいかに大切かなど、認知症と共に生きている人びとと'共に生きる'ことの意味を改めて認識させられました。なお続編の『私は私になっていく』では、認知症が進行しても内面の自己は残っていくと述べています。これも新しい発見でした。
クリスティーン・ボーデンの著書に出会ったころ、幸運にも、小澤勲著『痴呆を生きるということ』(岩波新書)という素晴らしい本とめぐり合いました。この本を読みながら、なぜか私は涙を抑えることができず、そして読み終わると心が洗われていました。不思議な魅力の本です。「南風」の職員にも勧めたところ、みんな強い感銘を受けたと言ってくれました。
トム・キットウッド著『認知症のパーソン・センタード・ケア ― 新しいケアの文化へ』は、しばらく前から認知症ケアの世界で注目されている本です。認知症ケアにおいて大切なことは「その人らしさ(Personhood)」を保つことだと教えています。そのためには、認知症の人びとに対する理解やケアのあり方を「古い文化(old culture)」から「新しい文化(new culture)」へ変えなければならないと訴えています。トム・キットウッドはこの新しい理念と方法を「パーソン・センタード・ケア」と名づけました。「その人を中心としたケア」という意味です。さまざまな分野の知識を網羅しているので、非常に内容の濃い本になっています。具体的な援助場面について述べた共著もあり、そちらのほうが読みやすいと思います。
最後に書籍ではありませんが、インターネット上のウェブサイトには認知症ケアに関する新しい動きを教えてくれるものがたくさんあります。カナダのアルツハイマー協会のウェブサイトには ― わが国や他の国々と同じように ― ずっと以前から、認知症と共に生きる人びとの生の声が掲載されています。そのなかで、認知症の人びとは自分たちのことを「はじめて希望を持つことができる世代」であると述べています。認知症の当事者たちがこう言えるのは、新しい薬が開発されていることと、地域ごとに彼らを支えるサポート・システムが存在しているからです。
もう一つ、これも書籍ではありませんが、インターネット上に「DASN International」というウェブサイトがあります。これは「Dementia Advocacy and Support Network」の略で、認知症の人びとが中心になって運営している「認知症の人びとのための擁護・支援ネットワーク」です。このウェブサイトには、認知症の人びとが自ら行ったスピーチや発言が掲載されています。最近、わが国でもこうした動きが見られるようになり、認知症と共に暮らしている人びとが自分たちの内面の世界を私たちに教えてくれています。いま、こうした当事者たちの意見を反映するかたちで、認知症の人びとに対する理解やケアのあり方が新しい時代を迎えようとしているのです。
- Aug
- 25
8 職員は満足しないかぎり職場を去っていく
高齢者ケア施設の経営者たちは、ふだん職員に向かって、これから大切なことは「入居者のサービス向上」や「入居者の満足」であると訴えます。施設間のサービス競争に負けないためです。競争に負ければ生き残れないと不安になっています。経営者たちは良いサービスこそが施設の命であると思っています。それはそれで素晴らしいことなのですが、そうした良いサービスを提供してくれるはずの職員の満足にはなぜか無頓着です(少なくとも、今まではそうでした)。職員が人手不足や忙しさを理由に言い訳をすれば、やる気が足りない、知恵を出せと、あからさまにイライラを顔に出します。ゆえに、多くの職員は、「私たちだけが経営者の見得のために犠牲になっている」と嘆くことになるのです。
職員は、入居者のための努力は惜しまないが、なぜ経営者もいっしょに汗を流してくれないのかと不満なのです。(私も経営者のはしくれなので、ここで経営者を代弁して一言。「私だけがこんなに苦労しているのに、どうして誰もそれを分かってくれないのだろう」)
これまで、どれほど大勢の人びとが高い理想をもって高齢者施設へ飛び込んできたことか。そして、どれほど多くの人びとが挫折を味わって施設を去っていったことか。それなのに経営者たちは言います。「近頃の職員は我慢が足りない」「なにを考えているのか分からない」「お金のために、すぐに職場を移っていく」と。はたして、これは本当でしょうか。
かの有名なマクレガーのX理論Y理論を持ち出すまでもなく、経営者のこうした主張は真実からかけ離れていると言えるでしょう。職員は、我慢して頑張ることがいやだと言っているわけではありません。他の施設が格別にすばらしいと思っているわけでもありません。彼らは心から知りたいのです ― このままこの施設で頑張っていれば、いつか幸せを得られるのだろうか?
職員が職場を去っていく理由はさまざまです。いまマスコミで職員の低賃金が問題視されているように、給料も大切な要因です。しかし、もっと直接的で切羽詰まった退職理由は、「職場にいやな人がいる」「職場の上司の顔を見たくない」でしょう。こうした状況に置かれた職員は、一日も早く職場から去ることを考えます。
もう少し長期的な理由としては、「うちの施設には理念がない」「うちの施設はみんなバラバラで、何かを改善しようとする姿勢がない」などが挙げられます。このような施設の職員には、いくら長く勤めても明るい展望が見えてきません。自分がそこに関わる意味が感じられなくなっていきます。こうして、その職員は、いつかチャンスがあったら職場を変わりたいと思いはじめます。
なぜ経営者は入居者のためのサービス向上だけを言い、職員の幸せについて言及しないのでしょうか。たしかに職場には目指すべき目標が必要です。みんなを鼓舞する理念がなければなりません。また、職場には、部下をいじめる上司がいてはいけません。しかしそれ以上に、職場には、職員を幸せにするシステムが存在しなければなりません。仕事に幸せを感じられない職員が入居者を幸せにすることなどあり得ません。サービスの向上を考えるのなら、同時に、サービスの提供をとおして職員が向上し、満足するシステムを構築する必要があるのです。
どの施設も、より良いサービスを提供することや、入居者の満足を追及することを理念としてかかげ、それを壁に飾っています。しかし、その陰で職員が泣いています。(こうした姿は経営者の目には入りません。なぜなら、自分の施設に限ってそんなことはあり得ないと、目をつぶっていたいからです)。私たちは、少なくとも入居者の満足と同程度に職員の満足を追及しなければなりません。とりわけ「南風」のような小さな施設にとって、職員がどう感じているかは致命的です。職員との信頼関係が揺らげば、いろいろな意味で立ち行かなくなります。大切なことは、祈るほどの気持ちで職員一人ひとりの幸せを考えることです。
- Aug
- 04
6 本の紹介: 『この気もち 伝えたい』
いま、私の手元に、伊藤守著『この気もち、伝えたい』(出版社:ディスカヴァー)という小さな本があります。書店の児童コーナーに並べられていても違和感のないような装丁で、表紙に赤いボールを抱えた子どもが描かれているかわいい本です。ページをめくると、一頁一頁に、私たちの普段のコミュニケーションをイメージしたかのような、子どもたちがボールを投げあっている絵があり、そのとなりに数行の短い文章が添えられています。
たったそれだけなのに、この本はとても大切なことを教えてくれます。分厚いコミュニケーションの専門書を読んでも頭に入らなかったことが、無邪気な子どもたちがキャッチボールをしている絵と、詩のような簡潔な文章を味わうだけで理解できてきます。まるで私たちと著者がすてきなコミュニケーションを楽しんでいるかのように、一つひとつの言葉がすとんと心のなかに落ちてきます。
ふだん私たちは他の人びとと心を通わせたいと思っています。それなのに、コミュニケーションをとおして苦さばかりを味わいつづけています。だから、人と接するのはもうこりごりだと思っています。この本は、そんな私たちに勇気と希望を与えてくれます。
ずっと以前、私はたまたまこの本を読んで感動し、その後、誰かに貸し出したまま忘れてしまっていました。そして最近、南風の職員がコミュニケーションについて勉強したいと言ってきたとき、とっさにこの本を思い出し、みんなに読んでもらいました。すると職員の多くが、いままで自分が何に悩んでいたのかはっきり分かったと感想を述べてくれたのです。この80頁足らずの'絵本'によって、コミュニケーションは難しいものだと決め込んでいた職員たちが自分自身を再発見していったのです。
著者は、コミュニケーションはキャッチボールだと言っています(以下は同書からの引用)。
コミュニケーションが
いっしょにはじめるものであるというのは、
幻想です。
はじめるのは、
いつも、どちらか一方。
あなたがボールを投げることからはじまります。
でも、
じぶんから投げるより、
むこうからくるのを待っていたい。
なぜって、
じぶんから投げて、
無視されると、悲しいから ・・・
著者は書いています ― 「自分からボールを投げるには勇気がいります。拒絶されるかもしれないし、ボールを他の人に渡されてしまうこともあります・・・それでも、よーく聴いて、相手の言いたいことをそのまんまに理解すること。それが'受け入れ'です・・・そして'受け入れ'があれば、違う考え、違う趣味、違う感じ方をもっていたとしても、いっしょにいれます」
著者の言葉を借りれば、私たちの誰もが「この気もち、伝えたい」と思っています。また誰もが、「きみの気もち、聞いてみたい」と思っています。そして、それがコミュニケーションのはじまりなのです。
このように、この本にはコミュニケーションの基本が書かれています。他の専門書とは多少語り口が違っていますが、無駄のないシンプルな文章で語られる大切なポイントが、頭ではなく、私たちの心に沁みてきます。もしみなさまが職場の人間関係で悩んでいらっしゃるのでしたら、まずあなた自身がこの本を手にとり、つぎに仲間に読んでもらうことをお勧めします。自分自身と仲間に対して、きっとやさしい気持ちになれるでしょう。
- Jul
- 29
5 お返しができなければつらくなる
私たちの社会には、人にものを贈ったり、人からものを貰(もら)うという慣習があります。その代表はお中元とお歳暮です。なかには「無駄だから止めましょう」と反対する声も聞こえるが、まわりを見ても止める気配がありません。それもそのはず、贈り物は経済に貢献しているだけでなく、それによって私たちは微妙に他人との付き合いのバランスをとっているからです。他人との関係のなかで暮らしているかぎり、止めることは不可能です。人からものを貰って返礼しなかったら、なんて言われるかわかりません。「変な人だ」と思われるのは軽いほうで、「風上にも置けない」とまで睨まれたら生きていくのがつらくなります。
このように贈り物には魔性が潜んでいます。ものを貰うと気持ちが委縮し、返すまで落ち着きません。ものを貰うと相手よりも自分の立場が下がったような気がするので、早く返して対等の人間関係をとり戻そうとする心理が働くのです。
お正月に、思いがけず、職場の同僚からたった一枚の年賀状(値段は50円)を貰っただけでも気分がふさいでしまいます。仕事始めまでに返事が届かなければ、言い訳を考えなければなりません ― 「昨日、スキーから戻ったら、あなたの年賀状が届いていたのでびっくりしたわ。申し訳ないけど、すぐに返事を書くので、二三日待ってください」と。
貰えば自分の立場が下がり、あげれば立場が上がります。いつも貰うだけの人は人間関係が切れていきます。それが許されるのは子どもだけです。だから子どもはお年玉を貰っても返しません。しかし大人は返さなければなりません。どうやら私たちはこんな掟のなかで暮らしているようです。
高齢者施設だって一つの社会です。世の中にあることは、ここにもすべてあります ― おそらく、もっと凝縮したかたちで。
日ごろ、施設の入居者たちはものを受けとる立場にいます。ここで言うものとは、食事介助、入浴、トイレ、散歩、言葉かけなど、職員が提供するサービスのことです。
だから入居者たちはつねに感謝します。「こんなに親切にしてもらって申し訳ない」と。なかには両手を合わせる人もいます。だからといって職員が偉いわけではありません。彼らは、ある意味では、つらいと言っているのです。いまのお年寄りは、他人の恩に報いることを教えられてきた世代です。ゆえに、感謝の気持ちを表すために(その申し訳なさを解消するために)彼らはお礼を考えます。
家族が面会に来てくれたとき、一人のお年寄りが、「いつも親切にしてもらっている職員にあげたいから」と、駅前の百貨店でおいしいお菓子を買ってきてほしいと依頼します。もちろん家族も同じ思いだから、すぐに買ってきます。そして一緒に職員のところへ持っていきます。「これ、みなさんで食べてください。いつも親切にしていただいているお礼です。」すると職員は、(本当は素直に貰ってあげたい気持ちもあるのだが)規則に反するからと断ってしまいます。貰えば上司から叱責されるのが目に見えているからです。押し問答のすえ、家族はそのお菓子を持ち帰ることになります。そして「こまったねえ。どうしたらいいのかしら」と更につらい気持になっていきます。ことの善し悪しは別にして、このやり取りは入居者や家族にとって、ある種のいじめと同じです。
[余談ですが、ある施設の職員からこんな話を聞いたことがあります。お菓子を持参した
家族が職員から受け取りを拒否され、困りはてた末に、「それじゃあ、ごみ箱にでも捨て
てください」と菓子箱をカウンターに置き去りにしたところ、翌日、その家族のところに宅
急便で菓子箱が送り返されてきたそうです。]
拒否されても、その人は職員にお返しをしたいという思いで一杯になっています。だから、何か別の方法を考えなければと知恵をしぼります。そして思いつきます ― となりにいる車椅子の人を助けてあげれば、少しは忙しい職員の役に立つかもしれないと。こうしてその人は、おぼつかない足で仲間の入居者の車椅子を押してあげます。それなのに、それを見つけた職員から、「だれがそんなことを頼んだのですか。転んだら私たちの責任よ。余計なことをしないでね。静かにしていてくれるのが一番だから」と、またしても冷たい言葉が返ってきます。どうしたらいいのだろう。いつも親切にしていただいている申し訳なさをお返ししたいだけなのに。
じつは入居者たちは職員にお返しをしているのですが、それが両者の目には見えません。入居者たちは介護保険料を払いつづけています。そのお金は国を経由して施設へ入り、そして給料のかたちで職員へ渡されます。毎月の施設利用料だって同じ仕組みです。彼らが支払ったお金が最終的には職員の手元に届いているにもかかわらず、職員も入居者もそれがわかりません。
もっと直接的なかたちで入居者から職員へお金が渡っていけば、入居者の気持ちも違ってくるでしょう。たとえば施設利用料の1割自己負担分を、「はい、この千円は入浴介助のお礼です」「はい、この五百円は食事介助のお礼です」と、サービスを受けるたびにじかに職員に手渡せば、その人の申し訳なさも和らいでいくかもしれません。
なにはともあれ、みんなが施設で心安らかに暮らすためには、入居者たちのお礼の気持ちを受け取ってあげることが大切です。もっとも良い方法は、お菓子に代わる別の方法でお返しできる機会を作ってあげることです。それが役割の提供なのです。
役割には、食事づくりに参加するなどの生活上の具体的なものもあるでしょう。あるいは、寝ているだけの人であっても、「あなたがいてくれるだけで、みんな励まされているのよ」という見えない役割もあるでしょう。豪華な外観と設備をそなえた施設が立派なのではありません。職員と入居者の間で上手にお返ししあえる循環システムを作り上げた施設こそが立派なのです。
- Jul
- 24
3 なじみの品物が手元にないと
施設で暮らすお年寄りにとって、所持品の持ち込みは非常に重要です。日頃なじんでいた品物が手元にあるだけで安心します。そうした品物が身近になければ、そのことばかり気にします。大切なものが見えないと、さみしくなったり、盗られたと心配になったり、家へ帰ると言い続けたり、さらに自分らしさが失せてしまいます。
ところが多くの施設には施設特有のルールがあって、できるかぎり所持品の持ち込みを制限しようとします。お年寄りが家族に伴われて入居のためにやって来たとき、最初に行われる手続き(儀式)が所持品のチェックです。その席では、施設での生活に必要な最低限の持ち物だけが選別されます。残りの品物は、収納場所がないからとか、ベッドのまわりが乱雑になるからとか、邪魔になるからとか、大切なものを失くすと困るからという理由で、家族が持ち帰ることになります。お年寄りにとって大切な品物は、かならずしも職員の目には大切なものとして映りません。亡くなった夫が遺していった(形見の)夫婦茶碗を持ち込んだお年寄りは、理不尽な説得の末に、それを取り上げられてしまいます。その人はもう、夫といっしょにお茶を楽しむことができません。
元気なころの社会的活躍をしめすトロフィーや賞状なども、職員にとっては無用の長物です。なぜなら、過去の栄光は施設内の人間関係の邪魔になるからです。いつもそれを見せつけられて、自慢ばかりされていたらたまりません。こうして入居者たちは過去の自分を証明する証拠品を手元から取り上げられていくのです。かりに、その人が、かつて社会的に立派な人物であったとしても、それを立証するものがないわけですから、その人の主張は根拠のない自慢話にしか聞こえません。こうして入居者たちは所持品だけでなく社会性までも奪われていきます。これは、入居後延々と続いていく入居者教育の第一歩なのです。
では、施設はこうした入居者教育(所持品の制限もその一つ)をとおして何をしようとしているのでしょうか。施設の職員が望む入居者像とは、みんな一律で、なるべく個性や自己主張を外に出さない入居者たちです。そのほうが仕事しやすいからです。みんなが個性豊かで、バラバラであったら、援助の方法も個別的にならざるをえません。それはいやなのです。施設のなかでは問題を起こすお年寄りに向かって、「あなたも他の人と同じようにしてくれないと困ります」という職員の声がよく聞かれます。このようなことが繰り返されると、いつか入居者たちは自分らしさをあきらめて、平均化していきます。この平均化してしまった姿こそ ― 職員の立場からすると ― 入居者たちが施設生活に適合した証しなのです。
入居者たちは、それまで馴染んでいた品物が手元にあることによって安心し、周囲に自分らしさを示すことができます。所持品にはこんなにも大切な意味が込められています。ですから、スペースに余裕のあるかぎり所持品の持ち込みを認めてあげる必要があります。家族にも所持品の持ち込みを奨励しなければなりません。居室にナイト・キャップが置いてあっても構わないじゃないですか。ひとり暮らしをしていたお年寄りが施設へ移るときに最も手放したくないのは、亡くなった配偶者の写真や位牌なのかもしれません。毎朝、その人が、その写真の前にご飯を供えている光景を思い浮かべてみましょう。亡くなったご主人に手を合わせ、新たな一日の無事を祈っている姿が想像できますか?
- Jul
- 15
2 「南風」を作った仲間たち
特別養護老人ホーム「南風」がスタートしたのは2003年4月のことでした。はたして私たちに施設運営ができるだろうかと関係者たちの気をもませ、たくさんの人びとのご支援を頂きながらのスタートでした。
オープンの1年前、それまでワン・マン・オフィスだった設立準備室には、私が直接声をかけた古くからの福祉の仲間や、その人たちが誘ってくれた新しい仲間がたくさん集まってきました。お互いによく知り合わないうちに、あちこちで熱い議論がはじまり、はたしてこの'南風丸'はどこへ行き着くのか、先が思いやられる船出でした。
準備室に集まった仲間はそれぞれが他の施設で働いていたので、みんなが一堂に会するのは休日か夜間でした。どの人も個性的で、一家言をもち、従来の施設のあり方に疑問を感じていました。理想と理想がぶつかりあい、誰もが自分の意見こそが正しいと信じていました。そのような場で、(責任者という立場上)もし私が「管理」とか「組織」とか「経営」などという言葉を持ち出せば、即座に冷たい視線が返ってくるのでした。資金の心配もさることながら、私はどうしたらこの人たちと良いチームを作っていけるだろうかと(祈る気持ちで)悩みつづけました。
あれから6年、いろいろなことを学びました。自他ともに認める「経営と数字」の音痴だった私は、準備室時代に経営に関する本を読みあさり、その後も(小説を読み映画を見る時間を犠牲にして)この経営という未知の世界を理解しようと膨大な数の本を読み比べました。
そのなかから学んだことは、経営の専門家といえども一人ひとりが違った考えを持っていること、流行の経営理論に振り回されてはいけないこと(専門家は責任をとってくれない)、もっとも大切なのは一緒に働いてくれる職員であること、ゆえに自分たちで考えて判断するのが最善であるということです。これは、ある意味では、専門書など読まなくても導き出せる単純明快な結論でした。
うれしいことに、準備室時代に集まってくれた人びとは今でも仲間として残っています。規模が小さくて、ささやかな活動しかできない「南風」が誇れることは、この仲間たちの存在です。昨今、世間には職員を「コスト」として切り捨てようとする風潮がありますが、私にとっては大切な宝物す。
「南風」には、もちろん職員や業務に関する組織図はありますが、堅苦しい上下関係はありません。ここには「管理」という名の「支配」は存在していません。また、多くの施設が取り入れている成果主義もありません。職員が喜ばないことはやらない方針だからです。成果主義は個々人の能力を高め、業績向上に結びつくと宣伝されていますが、それはどちらかと言えば都合よく職員とコストをカットするための仕組みで、結果として職員が不満をもち、組織が壊れていきます。職員の能力を比べて序列を作るよりも、一人ひとりのチームへの貢献を、そしてチーム全体の努力をこそ評価すべきなのです。私たちはチームで業務を行っています。チームのなかの人をバラバラに評価しても全体の力が高まるわけではありません。
最終的に私が行き着いた運営方針は、一人ひとりの職員の気持ちと働きを邪魔しないということです。どの職員も自分の考えをもっています。そして、どの人も他者のお世話が大好きです。だからこそ、この分野に飛び込んできたのです。放っておいても(邪魔をしなければ)、一生懸命に高齢者のケアに携わってくれます。その姿には頭が下がります。ですから、一人ひとりの意見をきちんと受けとめ、自由に行動できる環境を用意するだけで、みんなが最善を尽くしてくれるのです。
それでも私は、いつも職員に二つのことをお願いしています。第一は、高齢者が穏やかな気持ちでいられるようにしてほしい、あるいは高齢者を「その人らしく」させる職員になってほしいということです。私は、それができる職員とチームをつくり、いっしょに働きたいと思っています。逆に、つねに高齢者を困らせたり、つらい思いにさせる人は、私たちのチームに加わることができません。そういう人は、他者に関わるケアの仕事に向いていないのです(注:ケアとは他者を気づかうという意味です)。
第二に、もし職場の問題や高齢者の悩みに気づいたら、それを仲間といっしょに解決してほしいと願っています。たとえ失敗しても、それは問題ではありません。少なくとも、その人は努力したのです。新たに別の方法を考えて、ふたたび取り組めばよいだけの話です。いけないのは、職場の問題に気づいているのに、あるいは高齢者の悩みを知っているのに何もしようとしない人です。
職場で誰かがなにかを提案すると、ふだん周囲の人びとはこう言います ― 「なぜ、そんなことをしなければならないの?」「今まで通りでいいじゃない!」「あなた一人でやってみたら?」。こうしてその人は職場で孤立無援の状態に陥り、何も発言しないほうがいいと思うようになります。あるいは職場を去っていきます。その結果、施設は貴重な職員を失ってしまいます。ですから、失敗を恐れずに何かを実行しようとしている職員は、組織を上げて応援すべきなのです。
昨年末と新年度の初めに、行政の幹部の方々が「南風」を訪れてくれました。ここでの運営方法や職員教育について教えてほしいと言うのです。行政の方々は、「南風」がユニークな運営を行っていると考えているようでした。職員が明るく、自由に振舞っているようだと言っていました。ボランティア活動や地域住民との結びつきも評価してくれました。その人たちが帰ったあと、私が職員に感謝したのは当然です。この苦しかった5年間を仲間と共に耐え抜いてきて、本当によかったと思いました。
経営はきびしく、悩みは尽きなくても、大勢の職員がそれを埋め合わせてくれます。私たちの「南風」は、入居者、家族、地元の人びと、ボランティア、職員が等しく参加するケア・チームの形成をめざしています。そして、それぞれがお互いを必要としあい、それぞれがお互いを気づかいあうコミュニティを作りたいと考えています。
- May
- 15
1 パーソン・センタード・ケア
パーソン・センタード・ケアとは、とくに認知症のお年寄りが「その人らしく」暮らせるように援助することです。これはイギリスのブラッドフォード大学のトム・キットウッド教授が提唱したケアの考え方で、しばらく前から世界中の関係者たちの注目を集めています。彼の著書は、わが国でも『認知症のパーソン・センタード・ケア』として出版されています。しかし英語版の原題は『認知症について再度考える ― 認知症である前に、まず人間である』というふうに、従来の認知症ケアのイメージをくつがえす強いメッセージ性を伝えています。
アメリカのナーシングホーム(高齢者長期ケア施設)などでは施設ごとの独自性を出すために「パーソン・ファースト・ケア」「パーソン・ディレクテッド・ケア」等の名称も用いられていますが、'一人ひとりを中心にしたケア'という点ではみな同じ意味です。なおパーソン・センタード・ケアの対象には、施設で暮らしている入居者だけでなく、そこで働いている職員も含まれています。すなわちパーソン・センタード・ケアは、ケアを提供する人とケアを受ける人のすべてが「その人らしく」あることを目指しているのです。
パーソン・センタード・ケアでは、入居者たちが生きている喜びを感じたり、穏やかな気持ちで過ごしているとき、その人は「その人らしい状態」にいると考えます。逆に入居者が悲しみや寂しさ、退屈、孤独を感じているとき、その人は「その人らしくない状態」にいると見なします。ゆえに、この新しいケア方法の主旨は、お年寄りができる限り「その人らしい状態」で暮らせるよう、一人ひとりの状態やニーズに見合った個別的な援助を行うことなのです。
「その人らしさ」は一人ひとり異なっています。また、それは、その時々の気分によっても違います。ですから職員は、どうしてあげたらいいかを常に一人ひとりに尋ねる必要があります。たとえば、ある入居者がひとりで窓辺にすわり、外を眺めているとします。その人が穏やかな気持ちで外の景色を楽しんでいるのなら、それは「よい状態」であると言えます。しかし、その人が独りぼっちで寂しさをかみしめながら外を見ているとしたら、それは「よくない状態」であり、放っておくのはいけないことです。
パーソン・センタード・ケアでは、一人ひとりのニーズと気持ちに合わせた援助が求められます。それゆえ職員は、その人が、いつ、何をしたいか、どのようにして欲しいかを尋ねなければなりません。たとえば、いつ起きたいか、いつ、どこで、だれと朝食をたべたいかを確かめる必要があります。この点だけをとっても、パーソン・センタード・ケアは従来の施設で行われてきた「集団・一律処遇」とは相容れないものなのです。
最近、わが国でもパーソン・センタード・ケアの学習がはじまりました。しかし、パーソン・センタード・ケアが最終目標ではありません。じつは、この新しいケア方法の導入をとおして、いかに高齢者施設が生まれ変われるかが問われているのです。こうした改革は「施設のカルチャー・チェンジ」と呼ばれ、ケアのあり方、人間関係、入居者の自己決定と生活の選択、職員の働き方、権限の移譲、運営方針、命令系統など、組織内部で生起するすべての事柄の変革が求められていきます。
余談ですが、何年かまえに、認知症の人びとに対するパーソン・センタード・ケアという言葉をはじめて耳にしたとき、ふと「クライエント・センタード・セラピー」という言葉を思い出しました。これは、数十年前にアメリカの心理学者のカール・ロジャースが用いた有名な言葉です。彼の同名の著書(日本語のタイトルは『クライエント中心療法』)は、長い間、カウンセリングを学ぶものにとって重要なテキストとして位置づけられてきました。のちに彼は「パーソン・センタード・アプローチ」という言葉を用いています。
ロジャースは、その著書の中で、悩みを抱えて相談に訪れる人びと(クライエント)との間に共感的理解や、その人を受容する姿勢がなければ、よい援助的関係を築くことができないと述べています。彼は悩みや問題を抱えている人の相談にあたって、「その人らしさ」を大切にし、それをそのまま受け入れていったのです。おそらく、このロジャースが提唱したような援助的人間関係を大切にするという考え方が基底にあって、約半世紀後に認知症ケアの世界でパーソン・センタード・ケアが開花していったのだと思います。
ロジャースは"We should start from where the person is standing."と述べています。「私たちは、その人がいま立っているところからスタートすべきである」というこの言葉は、認知症とともに生きている人びとが今なにを感じ、なにを欲しているかを知ることに通じます。援助のスタート地点はこちら側(援助者側の都合や思い込み)にあるのではなく、あくまでも相手の側にあるのです。